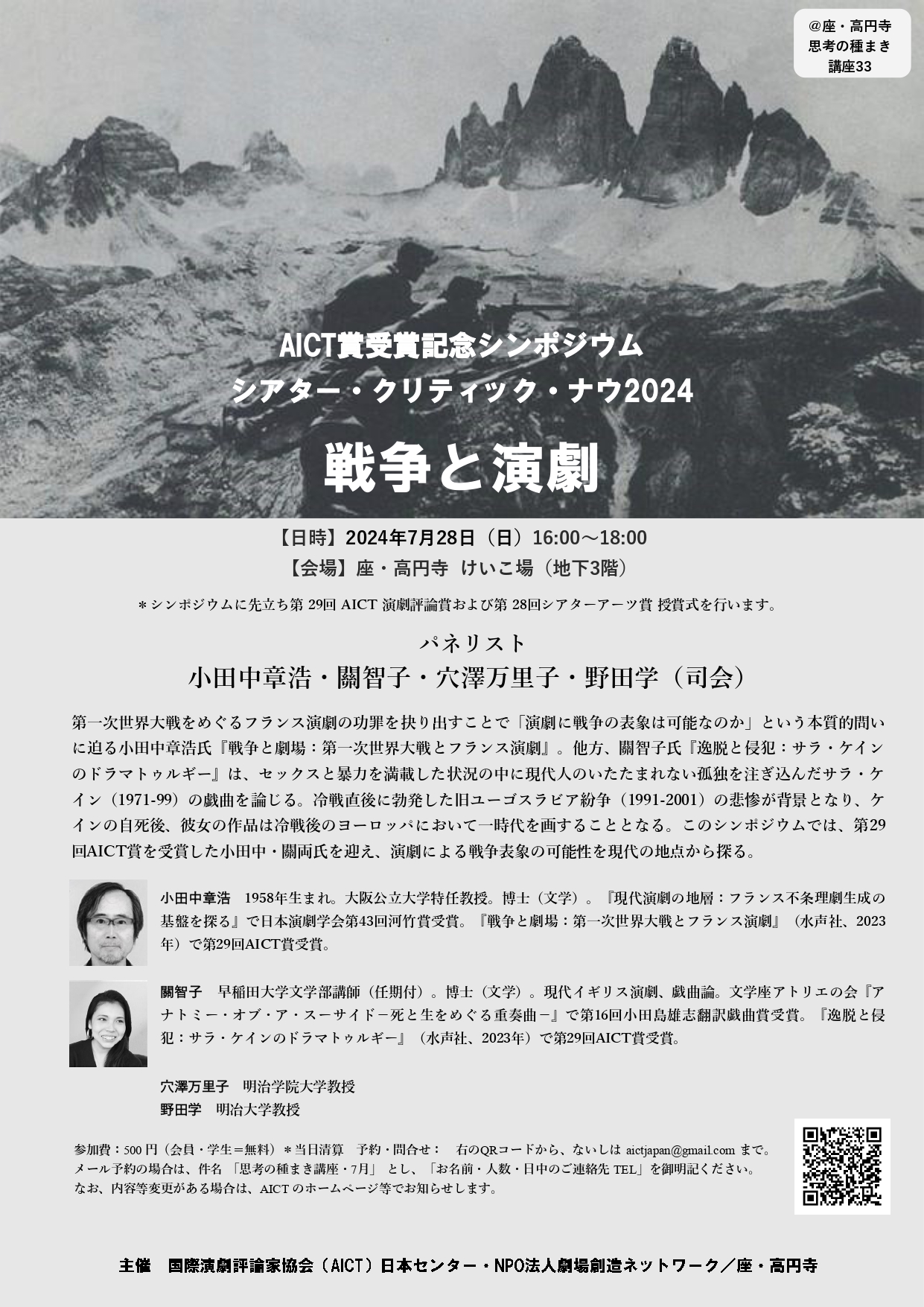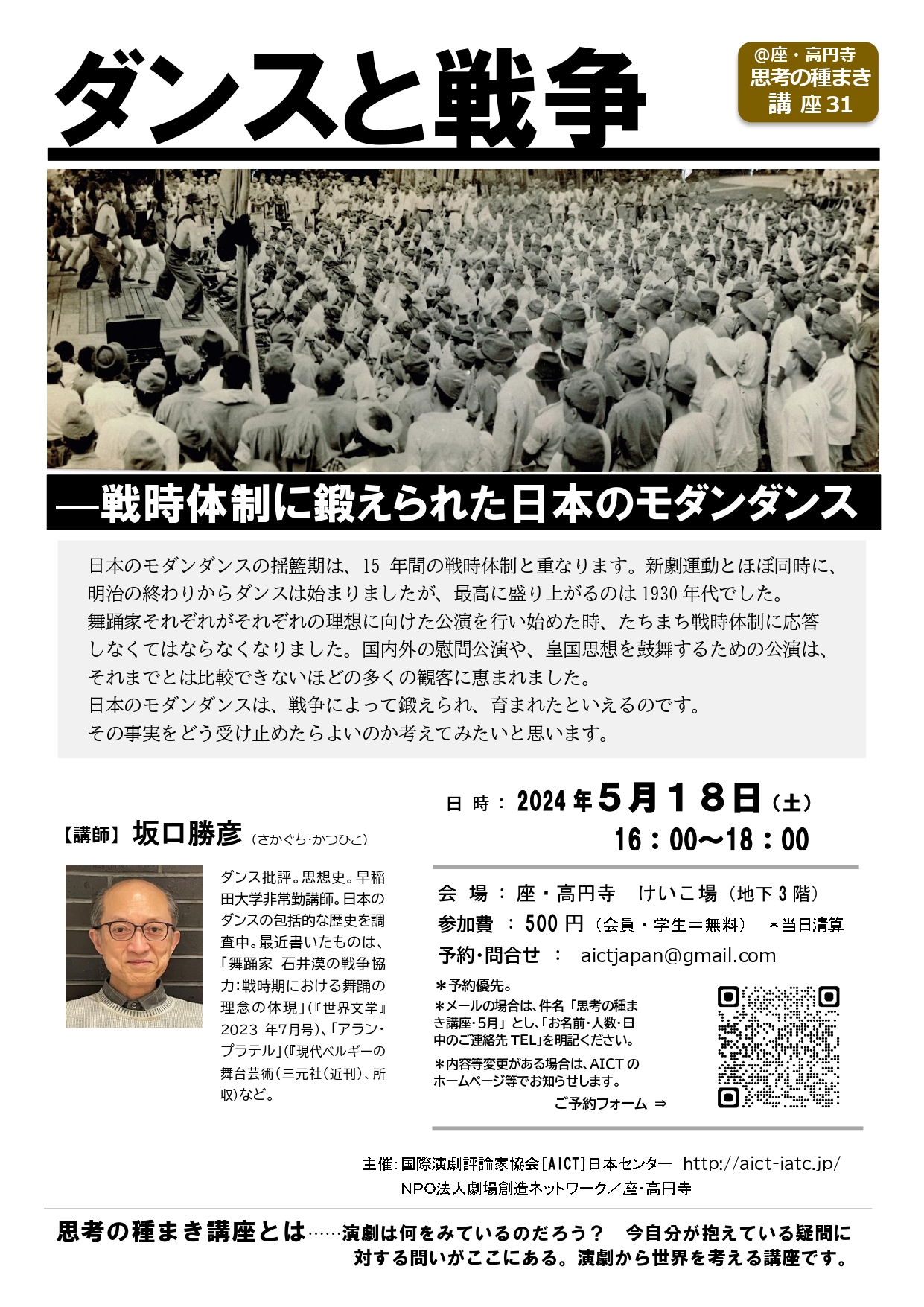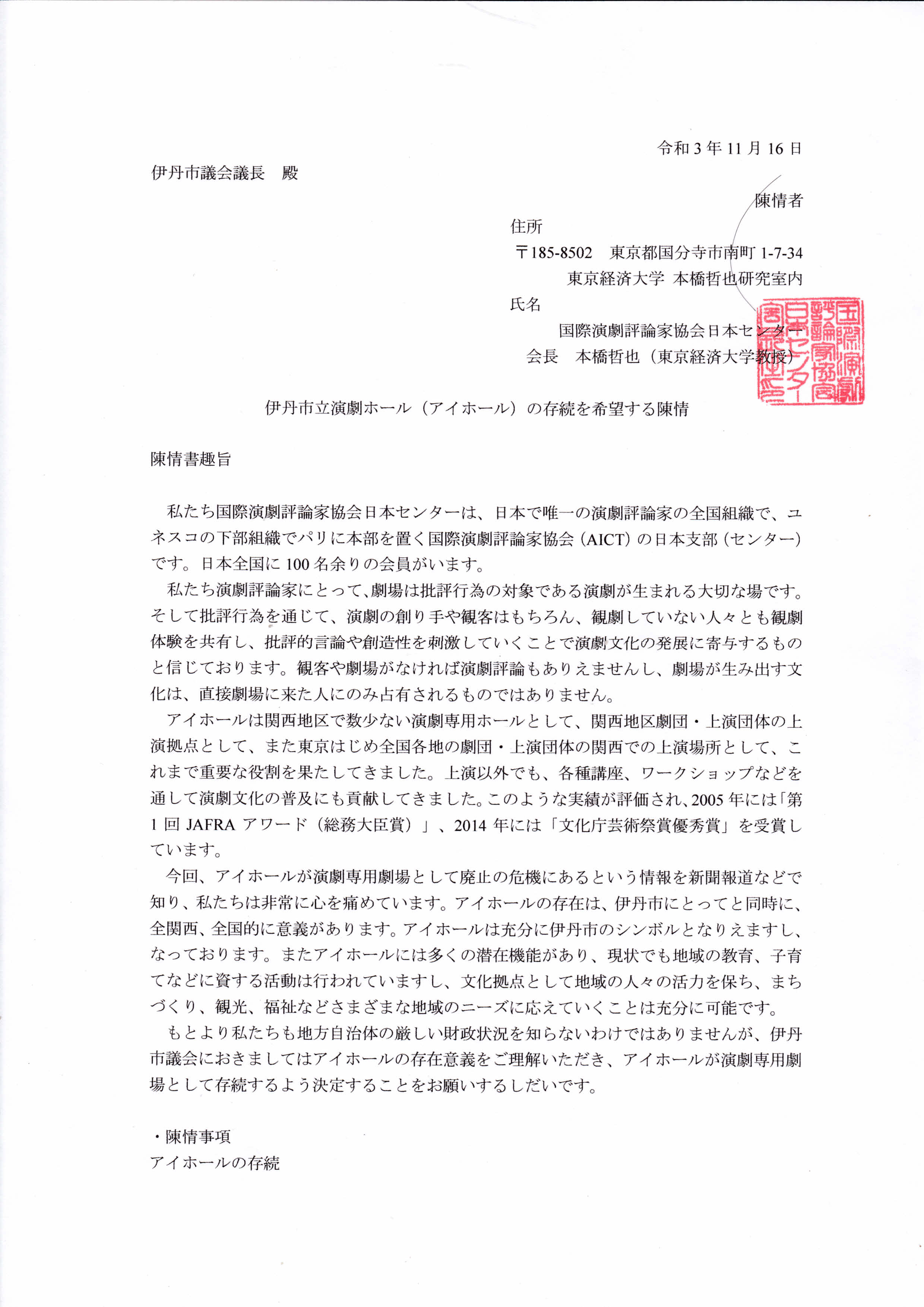AICT-IATCの事務局長ミシェル・ヴァイス氏経由で各国センターに転送されてきましたAICT-IATCロシアセンターからウクライナセンターへのメッセージの日本語訳を、急ぎ日本センターの会員諸氏とも共有いたしたく、英語とフランス語の原文とともに、以下に掲載させていただきます。
2022年2月25日 国際演劇評論家協会日本センター事務局
*********************
AICT-IATCウクライナセンター宛
AICT-IATCロシアセンターより
ロシア軍によるウクライナ侵攻について
同志へ
私たちは自国の政府によってウクライナの人々に行われている唾棄すべき軍事行動を非難し、この戦争への反対を明らかにするための署名をはじめ、あらゆる手段を用いて抗議を表明する所存です。
私たちは恥と無力感に苛まれていますが、皆さまの安全をお祈りしています。
そして私たちの願いは、演劇こそが常に人間らしさを支える空間であり続けること。
国際演劇評論家協会の使命の一つは、世界中どこでも表現の自由が促されること、文化の違いに橋を架けること、そして何時であろうと自由が束縛されるときには、それを守ることです。
私たち国際演劇評論家協会はロシア政府に対して、自国内における自由で平和的な手段に則った異議の表明を許し、他の独立国の境界を尊重することを要求します。
表現の自由こそ、いまや世界中の自由を愛する人々にとっての結束の絆です。
私たちはロシア政府に対し、現在の暴力を即座に停止し、侵略行動からの退却を強く求めます。
**************************
TO: Ukraine National Section, International Association of Theatre Critics (AICT-IATC)
FROM: Russia National Section, International Association of Theatre Critics (AICT-IATC)
RE: Russian Military Invasion of Ukraine
“Dear colleagues and friends!
We are horrified and condemn the military aggression that is launched against Ukrainian people by this government. We express our protest by all available means – manifesting and signing petitions against the war. We feel shame and helplessness. Be safe! Let theatre always stay a space for humanity.”
One of the primary missions of the International Association of Theatre Critics is to promote global free expression, the building of bridges between cultures, and the advocacy of freedom whenever it is constrained. The IATC calls upon the Russian government to allow the free and peaceful expression of dissent within its border and to respect the borders of independent nations.
Free expression is now a rallying point for freedom-loving people throughout the globe. We strongly urge the Russian government to cease and desist from its current path of oppression.
* * * * *
À : La Section nationale ukrainienne de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT)
DE : La Section nationale russe de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT)
OBJET : Invasion militaire russe de l’Ukraine
Le président et le secrétariat général de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT) ont reçu aujourd’hui un message de nos collègues de la section russe de l’AICT, destiné à nos collègues de la section ukrainienne. Nous diffusons ce message par tous les canaux disponibles.
« Chers collègues et amis !
Nous sommes horrifiés et condamnons l’agression militaire lancée contre le peuple ukrainien par ce gouvernement. Nous exprimons notre protestation par tous les moyens disponibles – en manifestant et en signant des pétitions contre la guerre. Nous ressentons de la honte et de l’impuissance. Prenez garde ! Que le théâtre demeure toujours un espace pour l’humanité. »
L’une des principales missions de l’Association internationale des critiques de théâtre consiste à promouvoir la liberté d’expression dans le monde, la construction de ponts entre les cultures et la défense de la liberté chaque fois qu’elle est contrainte. L’AICT appelle le gouvernement russe à permettre l’expression libre et pacifique de la dissidence à l’intérieur de ses frontières et à respecter les frontières des nations indépendantes. La liberté d’expression est désormais un point de ralliement pour les personnes éprises de liberté à travers le monde. Nous demandons instamment au gouvernement russe de cesser et d’abandonner sa trajectoire actuelle vers l’oppression.